|
華音(かおん)は、強く吹き付けてきた風に細く身を震わせた。 北国であるネルトリヒラントは一年を通して季節の変化に乏しい。それでも、細く冷え切っていく空気の下で秋から冬への世界の変貌を感じ取ることはできる。ゆっくりと冷えていく空気の鋭さは、研ぎ澄まされた細剣のそれに似て、肌にちりちりとした痛みをもたらすような気がした。 あるいはそれは、この国の現状のせいなのかもしれない。華音は髪を風に遊ばせながら、遠く眼下に広がる大地を望んだ。 時間がたてばたつほど、空が鋭く細るほど、塔から見下ろす世界からはひとつ、またひとつと「音」が姿を消していく。音使い(ラオトザムラー)の少女は自らの主のようにそのような音たちを「聴く」ことができるわけではないが、それでもこの国を暗い静寂が覆っていっていることには気づいていた。 「また、一年が経ったね」 突如隣から澄み渡った声がもたらされた。華音が驚いて振り向くと、視界の端に金糸が踊る。 いつの間にか、仕えるべき姫がそこにいた。 侍女の姿を認めると、姫――琉姫(りゅうき)は屈託なく微笑む。しかし、その微笑はすぐに悲しげに沈んでいった。華音は知らないうちに息をのんでいた。 見た目自分よりもずっと小さく幼い主君の碧眼は、時としてこの年頃の少女にはないはずの物憂いげな光を帯びる。そんな時の彼女は、自分よりもずっと、大人びて見えた。同時に、どこか遠くへ行ってしまいそうだと思ってしまうほどに。 「僕がこの塔で『一年』を積み重ねていくごとに、王国からは音が消えていく――」 消え入りそうな姫の独白に少女は意識を引きもどされた。 同時に、琉姫がどういう意味で一年、という言葉を使っているのかを察した。 華音はしばらく逡巡したのち、すっと琉姫の方を見て胸に手を当てる。 「姫様、何か望まれるものはございますか?」 いつもの何倍も意識して、恭しい台詞をひねりだす。 海の青を思わせる瞳が華音を捉え、驚きに見開かれた。それに対して彼女は向日葵(ひまわり)のような笑顔を向ける。だが心の中では、嘲りの冷笑を浮かべていた。 とんでもない卑怯者だ。この塔の中で叶えられることは限られているというのに。 もし琉姫が「外へ出たい」と言い出したらどうするつもりなのか。塔から出ることは、如何にしても叶わないというのに。 否。 この綺羅琉姫という少女は、華音にそんな我がままを言うことはない。それを承知で彼女は今こうして、微笑んでいるのだ。 ああ、本当に…… 「いつも通りでいいよ」 いつも、この小さなお姫様はそう言って笑うのだ。 「華音が隣にいてくれれば、それで僕は幸せ」 金の髪とドレスをなびかせ答える少女の姿は、華音が知っている以上に泰然としていて、美しかった。姫様、とあえぎのような声を漏らした華音は侍女としての微笑を崩してうつむく。そのうちに、琉姫の視線は再び塔の外へと注がれていた。 「でも、もしひとつどうしようもない我がままを言うとしたら」 穏やかな声に、華音は顔を上げた。琉姫が今にも歌を歌い出しそうな表情で続ける。 「この、暗く沈んだ王国に、音楽禁止という掟に、人々の悲しい旋律に、負けないくらいの強く明るい旋律を奏でる音使いが、僕の前に現れてほしい」 朗々とそう言いきったあと、ふと口をつぐんだ琉姫は、再び華音に向き直って苦笑した。 「なんて、本当にどうしようもないお願い事だよね」 困ったように言う少女。 彼女に付き従う侍女であり、彼女を守るべき存在として遣わされた者は、主に向かって母親のような声音で「いいえ、そのようなことはありませんわ」と断言した。 こうしてまた、季節は過ぎ去っていくのだ。 二人がこのとき望んだような音使いの少年が塔を訪れるのは、それから数カ月後のことである。 ◇ 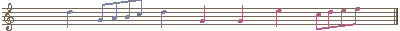 私が華麗にスルー決め込んだ琉姫のお誕生日を、 こんな素敵な小説作品で祝って頂いちゃいました…! こんな会話、本当に二人の間で交わされていたように思います。 人々の心が歌わなくなる様がとても丁寧に、繊細に描かれていると感じました。 今本編で執筆中のシーンに素敵な臨場感を齎してくださったのではないでしょうか…。 この先、国を変え得る少年が本当に現れる訳です。 その可能性の提示がとても心に響きました。 七海さん、本当に素敵な作品をありがとうございます。 キャラクターの誕生日とは言え、素敵すぎて、なんというか…畏れ多いです!!! それくらい嬉しかったです!本当に、有難うございました!! 蒼井七海様の素敵サイトはこちら→  |